3月21日から72時間限定で無料公開されていた鬼頭莫宏氏の名作『ぼくらの』を久しぶりに読み返しました。
14年ぶりに『ぼくらの』を再読して
『ぼくらの』21日から72時間限定で全話無料公開へ。小学館「ビッコミ」にて、”鬱マンガ”と称されるも細やかな心情描写から命の大切さを考えさせられるロボットSFの名作
変わらぬ感想と、新たな視点
14年前に書いた感想を改めて読み返すと、基本的な印象は変わらない部分が多いものの、新たな視点で見えるものもありました。
コミックぼくらのが大変面白かったです(ネタバレアリです) | Office NaKao
特にカナ / 宇白可奈のエピソードに対する印象が大きく変わっていました。
以前は、幼い少女が犠牲になるという展開やその繊細で不憫な作画にばかり目が行き、カナの本質を見落としていました。
今回改めて読むと、彼女は血の繋がらない兄・ウシロ / 宇白順と彼の実母・田中美純を引き合わせることに強い希望を抱く、誰よりも強い人間として描かれていたのだと感じました。
映画「アルマゲドン」と漫画「ぼくらの」の自己犠牲の描写違い(ネタバレあり) | Office NaKao
改めて理解できなかったこと
今回の再読で、根本的に理解できなかった部分がより明確になりました。これは、自分にはまだ理解しきれない深い人間性の解釈があることを示しており、それを感じること自体が心地よい経験でした。
キリエと対戦相手の少女の邂逅
人に命を譲ることを正しいと感じる性格であるキリエ / 切江洋介が、対戦相手の少女が自らのリストカット痕を見せられたことで何かを共有し、従姉のカズちゃんの未来に希望を託しつつ戦うという流れには、完全には共感しきれませんでした。
むしろ、対戦相手がカズちゃんに重なったことで戦意を失うのでは?と考えてしまいました。
カナがウシロと田中美純の関係に求めたもの
カナの家族への憧れや救いを求める気持ちは理解できますが、彼女が思い描いた「もしかしたらあり得たかもしれないハッピーエンド」を、具体的にイメージすることはできませんでした。田中美純の言葉に影響を受け、彼女がウシロに名乗り出なかったことには、ある種の納得感を覚えました。
一方で、二人が親子として会う機会を失った瞬間にカナが叫ぶ場面の描写には、非常に複雑な心情がにじんでおり、その心の動きをより深く理解したいと強く感じました。
ウシロの対戦相手の意図
包帯に包まれた痛々しい姿の対戦相手は、世界やゲームに絶望し、復讐のような形で、自分の世界やウシロたちへの嫌がらせをしているように見えました。
物語としても、またエンターテインメントとしても、「対戦相手の世界の人間すべてを殺す」という過酷な状況にウシロが巻き込まれただけで、十分に意味のある展開だったように感じられます。
しかし一方で、ある種の負の感情に正直であれば当然見えてくるはずの、対戦相手の心理を見落としていたのではないか?そんな問いも浮かび、考えさせられました。
改めて腑に落ちたこと
死を受け入れた先にある物語
『ぼくらの』は、混乱や感情の暴走といった「分かりやすい人間ドラマ」はカコ / 加古功のエピソードに集約されており、それ以外のエピソードでは、登場人物たちは死を受け入れ、論理的思考に基づいて行動しています。この構造によって、読者もまた死を強く意識することでしか到達できない思考へと誘導されるのだと感じました。
残酷で喪失感に満ちた作品でありながら、読み進めるほどに家族や大切な人に優しくしたくなる読後感を残すのは、本作の大きな魅力です。
自滅の可能性が極めて高いゲーム性
『ぼくらの』に登場する戦いは、実は自滅の可能性が極めて高いゲームだったことに気づきました。
カコやキリエのエピソードでは、パイロット自身やその人間関係が原因で敗北の危機に陥る。
マチ / 町洋子のエピソードでは、世界の住人の思惑や誤解によって状況が悪化する。
一方で、コモ / 古茂田孝美やウシロのエピソードでは、対戦相手が戦意を喪失したことで勝利を得ています。
つまり、このゲームでは自らの弱さや環境の影響で敗北する可能性が高く、戦いそのものよりも、それを取り巻く心理や状況の方が重要だったのではないかと再認識しました。
時代が変わっても色褪せない魅力
『ぼくらの』の登場人物たちは驚くほど達観した死生観に達しており、論理的思考と行動力に長けています。一方で、作中の世界には、SNS時代の現代に通じる「暴走する感情」や「同調圧力」に満ちた世論の気配が感じられました。
それらが入り混じる、複雑な思考や状況整理を、緻密で丁寧な最小限の言葉や作画によって自然に理解させる表現力こそが、本作を不朽の名作たらしめている要因なのだと改めて実感しました。
まとめ
14年ぶりに再読した『ぼくらの』は、変わらぬ魅力と新たな気づきを与えてくれました。キャラクターたちの死生観や論理的な思考は色褪せることなく、むしろ現代の社会状況とも共鳴する部分がありました。物語の中に散りばめられた人間心理の奥深さに、改めて圧倒されると同時に、自分にはまだ理解しきれない部分があることも再認識しました。残酷な世界観の中で描かれる「優しさ」や「希望」は、読むたびに異なる視点をもたらし、考えさせられます。『ぼくらの』は、時代を超えて読み継がれるべき名作であると改めて実感しました。







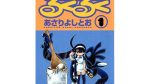








 代表.中尾治人(ナカオハルヒト)
代表.中尾治人(ナカオハルヒト)